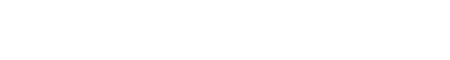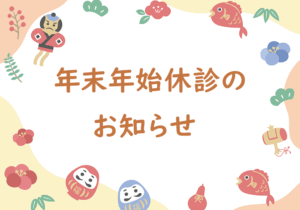安全な歯科治療のために知っておきたい歯科麻酔

こんにちは。熊谷デンタルクリニックです。
10月13日は「麻酔の日」でした。
皆さまは歯科治療の際に麻酔を受けたことはありますか?
今回は「麻酔の日」にちなみ、歯科麻酔の主な種類や、麻酔を受ける際の注意点についてお話しします。
歯科麻酔の種類
歯科麻酔には、大きく分けて3つの種類があります。
表面麻酔
麻酔薬を歯ぐきに塗ることで、表面の感覚を麻痺させる方法です。
歯に直接麻酔をする場合は注射が必要ですが、その際の針の痛みを和らげるために表面麻酔を行います。
処置では、お口の中にガーゼやコットンを入れ、麻酔薬が流れないようにしながら、効果が出るまで数分待ちます。
浸潤麻酔
歯そのものに麻酔をする方法で、最も一般的な麻酔です。
歯ぐきに麻酔薬を直接注射することで、治療箇所の痛みを抑えます。
注射時の痛みを減らすため、極細の針を使ったり、麻酔薬を体温と同じくらいに温めたりする工夫をします。
伝達麻酔
主に親知らずの抜歯や、下顎の奥歯の治療など、強い麻酔効果が必要なときに使います。
広い範囲がしびれ、長い時間効果が持続するのが特徴です。顎の近くにある太い神経のそばに麻酔薬を注射します。
麻酔を受けたときの注意点
副作用
麻酔治療を受けたときに、以下のような副作用が出る場合があります。
表面麻酔の場合
- むくみ
- じんましん
- めまい
- 眠気
- 不安感
- 興奮
- 嘔吐
浸潤麻酔・伝達麻酔の場合
- 吐き気
- 手足の震え
- しびれ
このような症状が現れた場合は、すぐに歯科医師へ伝えてください。
また、麻酔にアレルギーがある方や、過去に副作用を経験したことのある方も、事前に必ず申告してください。
麻酔の効果時間
表面麻酔は約10~20分、浸潤麻酔は約1~3時間、伝達麻酔は約3~6時間程度効果が持続します。
麻酔によっては歯科治療が終わった後も、しばらくは麻酔が効いている状態となるため、自宅での過ごし方にも注意が必要です。
自宅での過ごし方
麻酔が効いている間は、感覚が鈍くなっているため、痛みや刺激に気づきにくくなります。
そのため、食事をするときに頬の内側や唇、舌を噛んでしまうことがあります。麻酔が切れるまでは、食事を控えるようにしましょう。
また、熱い飲み物などもやけどをする恐れがあるため、控えるようにしましょう。
まとめ
歯科治療で麻酔を受けた際は、副作用や自宅での過ごし方に気を付けましょう。
特に、高血圧や心臓の病気がある方や、過去に麻酔で副作用を経験した方は、事前に歯科医師にお伝えください。
麻酔後、気分が悪くなったり副作用が出たりした場合も、すぐに歯科医師にお伝えください。
当クリニックでは、自費治療で静脈内鎮静法(点滴麻酔)を行なっています。
鎮静剤を静脈内に入れることで、リラックスした状態で治療を受けることができますので、親知らずの抜歯などを受ける方で、「治療に不安がある」「怖い」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。